こんにちは、楽しい育児パパです。
突然ですが――
「パートナーとの育児・家事分担、うまくいってますか?」
仕事に追われ、家事と育児に追われ、自分の時間なんて1ミリもない。
子どもは可愛いけど、家のことを“どっちがどれだけやってるか”でイライラしてしまう……。
そんな状況、かつての我が家でもありました。
でも今では、「うち、うまく回ってるな」と思えるようになりました。
そのカギは、“子育てをチーム戦”と捉えることでした。
この記事では、我が家で実際に行っている「家事・育児の分担ルール」と「ケンカにならない役割の決め方」について、リアルな経験を交えてご紹介します。
「手伝う」じゃない、「一緒にやる」がスタートライン
僕も最初は「何か手伝おうか?」と口にしていました。
でもこの一言、地雷なんですよね(特にワンオペが続いているパートナーにとっては…)。
なぜなら、「手伝う」という言葉には、
“本来の担当はあなた。でも余裕があったら手を貸すよ”という前提があるから。
これに気づいたとき、「これはマズい」と思いました。
家庭は会社と違って、上下関係も責任者もいません。だからこそ、チームとして役割を“自分ごと”にする意識が必要なんです。
我が家の分担ルール:明文化と柔軟さのバランス
我が家の分担は、以下のようなルールで成り立っています。
基本は「担当制」だけど「交換可能」
- 平日の保育園送り迎え:ママ
- 夕方のごはん作り:ママ
- ゴミ捨て:チチ(=僕)
- お風呂:交代制(どちらか早く動ける方)
- 洗濯:ママメイン、たたむのはパパ
- 食器洗い:チチ
- 子どもの寝かしつけ:ママ(でも気絶してたら交代)
重要なのは、**「原則は決めておく」けど、「相手が疲れてそうだったら代わる」**という柔軟さ。
お互いに「ありがとう」を伝え合うことを忘れなければ、多少の偏りが出てもギスギスしません。
分担を決めるときに話し合った3つのこと
役割分担って、話し合いが一番大事です。
我が家では、以下の3つを基準に役割を決めました。
①「得意・不得意」で割り振る
料理が得意なパートナーにはごはん担当を。
僕は食器洗いや洗濯物たたみの方が向いてたので、そちらを引き受けました。
②「時間帯で動ける方」がルール
平日は僕が会社に出社しますが、夕方早めには帰ってこれるので、空いている時間で
出来ることが多い洗い物や食器洗い、土日は積極的に家事・育児をカバーしています。
③「気づいた人がやる」が基本の空気感
担当制にしすぎると、「これは自分の仕事じゃない」と思いがちなので、
誰かが忙しいときには自然に補い合えるよう、“気づいたらやる”文化を育てました。
子どもが加わると、チーム戦はさらに面白くなる
最近では、2歳の上の娘も少しずつ戦力になってきました。
- 「○○取ってきて~」でお手伝い係に
- 洗濯物を一緒にたたむ
- 食卓にフォークを並べる
こういう「子ども参加型」の家事は、親としてもラクになるだけでなく、子どもの自己肯定感や“非認知能力”の育成にも効果的なんです。
トラブルを防ぐコツ:「ありがとう」と「見える化」
いくら分担を決めても、疲れていると相手への不満は募るもの。
そんな時に役立ったのが、以下の2つ。
「ありがとう」を意識的に伝える
- 「今日も洗濯ありがとう」
- 「お迎え間に合って助かったよ」
- 「寝かしつけてくれてありがとう」
感謝の言葉は、夫婦の潤滑油です。口に出すだけで、お互いのストレスがぐっと減ります。
「やったことリスト」で見える化
付箋やホワイトボード、またはLINEで「今日やった家事・育児」を共有。
「自分ばっかりやってる」ではなく、“チームでやってる感”が強まります。
子育ては、チームで育ててこそ楽になる
子どもは可愛いけど、子育ては正直ハード。
だからこそ、「一人で頑張る」ではなく、「チームで支え合う」ことが大切です。
夫婦でなくても、実家の親、保育園の先生、友人、地域の支援サービス…
どんな形でも、“一人で抱えない”という意識が、家庭を救ってくれます。
まとめ:家庭は“会社”じゃなく“サッカーチーム”みたいなもの
- 得意なことを活かし合う
- 状況に応じてポジションチェンジする
- 困っていたらすぐに助け合う
- ゴールを決めたらみんなで喜ぶ
家庭って、そういう「チームプレー」が大事なんだと思います。
「子育てはチーム戦」。
この言葉が、あなたの家の雰囲気を少しでも前向きに変えるきっかけになれば嬉しいです。

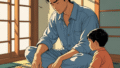

コメント